学級懇談会は面倒、忙しくて準備に時間をかけられない、と感じていませんか?
私は若いころ学級懇談会が憂鬱でした。でも、繰り返すうちにそれほど苦痛でなくなり楽しみにもなっていきました。
そんな気持ちになれる方法について書きます。
学級懇談会が苦痛に感じる原因
学級懇談会はなぜ苦痛に感じるのでしょう。そう感じる理由を考えてみました。
準備をする時間がない
日々忙しい中で懇談会の準備もしないといけない、ということがまず気が重いです。
学級懇談会は授業参観の後に行われることが多いので、まず参観授業をどうしようかと考えなければいけないし、教室の整頓も気になるし、その上学級懇談会の準備もしなくちゃ、となりがちです。
授業も教室の整頓も普段からちゃんとしているから大丈夫と思えれば良いですが、保護者に見られると考えるともう少し見栄え良くしたい、と思ってしまいます。
私はこの、もう少し見栄え良くしたいという考え方は、普段を見直すという意味で前向きで良いと思います。ただ、それでイライラする(余分な仕事だ、嫌だと思う)なら、割り切って普段のままでいいや、と思うようにしましょう。
私が保護者の立場で担任を見るとき、細かいことは気にしなかったので、ほとんどの保護者は気にしていないと思います。(担任は私が教員だと知っているから私に見られるのは嫌だったかな、とは思いますが)
保護者は自分の子どもしかほぼ見ていません。他の子の授業態度や担任の先生の姿も目に入りますが、それを重要なことだとはあまり思いません。
学級懇談会に向けての準備は、教室の整頓や授業を少し見直す、懇談会を滞りなく進める、くらいの気持ちで十分です。
もちろん、私は保護者に伝えたいことがある!保護者と意見交流したい!と意気込んでも良いです。でも気合を入れても空回りする可能性が高い(後ほど理由は書きます)ので、ほどほどが良いと思います。
保護者が前向きでない
小学校だとそうでもないかもしれませんが、中学校だと学級懇談会に保護者の参加が非常に少ないことがあります。
参観授業は見るけれど学級懇談会は出席せず帰る保護者がかなりいます。
でも、この状況に対して管理職が「保護者の学校に対する関心が低すぎる!もっと参加者が増えるように担任は努力しなさい」と言ったり、ベテラン教師が「親さんが残ってくれるように楽しい話を準備しています」などと言うのはいらないことです。
中学生ともなると母親も働いている場合が多いので、学校に行くより自分の時間が欲しいのです。子どもが元気に学校に行っているので任せています、担任の話を聞くのは三者懇談で十分です、と思っているのです。
無理に来させる努力は必要ありません。勤務校によって傾向は違いましたが、学級懇談会の参加人数が一桁という学校も経験しました。気にしないことです。
保護者からの苦情を聞く場になってしまう
逆に大勢の参加があって、言いたい放題言われる場になってしまうという恐怖があります。
私の場合、初任で担任だったときに色々言われました。(私の自治体では今は初任者が担任を持たないように配慮されていますが、昔は初任でも担任を持つことがありました。)
ただ思い返すとそんなことはそのときだけでした。私の失敗が多くてクラスが落ち着かなかったので、言われるのは当然でした。
2年目以降は厳しい意見はほとんどなかったです。クラスが落ち着いていれば保護者は特に文句は言わないものです。
それでも若い頃は1年目の苦しさが頭にあるので、懇談会はいつも緊張していました。今思えばいらない緊張だったと思います。リラックスして臨みたいですね。
学級懇談会の意義
まずは学級懇談会について心配しがちなことを書きましたが、ここからが本題です。学級懇談会をする意味は何でしょう。
保護者の思いを交流する場の提供
一番は保護者の気持ちや意見を聞く場を作るためです。
伝えたい思いのある保護者が他の保護者の前で話す場を作ることで思いを共有し、意見を交換する場を提供する、ということです。
ただ実際は学級懇談会の場で問題提起発言をする保護者は滅多に見かけません。クラスが荒れていて多くの保護者が心配している場合は別ですが。
学級が平穏なときに学級懇談会に来る親さんは「担任の先生の話を聞こう」「懇談会に出席すると先生に良い印象を持ってもらえるかも」「この担任の学級懇談会の雰囲気を見てみよう」くらいの気持ちです。
ですので担任が気合いを入れて「皆さんのご意見を聞きたいのです!」と発言を強要する空気を出すと引かれます。
軽い感じで一人一言ずつ話す程度の交流ができれば良いのです。そういう交流ができるように場を回すのが教師の役割だと考えましょう。
具体的なやり方は後程書きます。
担任のことを理解してもらい、保護者に安心感を与える
もう一つの意義は、担任の考えを伝えて安心してもらうことです。
学級懇談会の内容は様々考えられますが、担任の話が多くなるのが一般的です。担任の話を聞くことで、担任の考え方や人柄を保護者が知ることができます。安心してもらえるように、落ち着いて話しましょう。
もちろん話す内容はちゃんと準備しておきます。
趣味や家族の話をして自分を知ってもらうのも良いですが、それはほどほどにします。
保護者が一番知りたいのは「自分の子どもにとって良い担任かどうか」です。趣味の話をして「うちの子と気が合いそう」と思ってもらえれば良いですが、「うちの子とは気が合わなさそう」と思われる可能性もあります。
ここは無難に「クラスの様子」や「こんなクラスにしていきたい」という話を中心にしましょう。
学級懇談会をどのように行うか
それではここからは学級懇談会の進め方を具体的に書きます。
学級懇談会の進め方は学校全体や学年で雛形を決めている場合もあるかと思います。また、学級懇談会の進め方は懇談会の目的によって変わると思いますが、ここでは授業参観の後に行われる定期の会とします。
私の経験から内容の例を挙げるので参考にしてください。
机列、名札について
机列は参加人数を見て臨機応変に考えるといいでしょう。
クラスの半数程度以上参加がある場合は「お子さんの席に座ってください」とお願いし、全員黒板の方を向く講義形式で行いました。
人数が多いときは保護者同士が交流する時間があまり取れないので、担任の話が聞きやすい形が良いと思います。
参加人数がクラスの半分より少ないときは自由に席に付いてもらい、机を内側に向けて座談会形式にしました。お互いの顔を見られる方が話しやすいと思うからです。
名札があると良いですが無理に準備する必要はありません。最近は不審者の侵入を防ぐ意味で保護者が名札を首から下げるルールにしている学校があります。その場合はありがたいですね。
クラスの様子の紹介、担任の考え
最初の学級懇談会では「今のクラスの様子」と「こんなクラスにしたいという担任の願い」を話すと思います。2回目以降も「今のクラスの様子」と「今後もこんなクラスを目指したい」という話をするとよいです。
このとき一番心掛けたいことは「保護者に安心感を与えること」です。
もしも学級で生徒がほぼ全員が知っている問題(例えば、いじめがあり個別や全体で指導した、というような)があった場合は、指導の概要を伝えた方が良いです。
問題について子どもから部分的に聞いている保護者は少なからず不安を感じているでしょうから。
学校の出来事を話さないタイプの子どもだと初耳の保護者もいると思いますが、問題が起きたときは担任がきちんと対応するということを伝える機会になります。
もちろん話す時点で問題が解決済みであることが望ましいです。
生徒個人の名前は出さずに問題の概要と指導の流れだけを話します。そして「気付かれたこと気になることは遠慮なく担任にお伝えください」と話します。
各家庭でその問題について話題にされると思いますが、学校での指導が適切であれば、問題が解決済みであることや今は問題なく生活していることが子どもの口から伝わるはずです。
特に問題なく通常の生活ができている場合は、最近のクラスの様子を良い点8割、課題点2割くらいで話しましょう。
良い点は、子どもたちの成長したところ、行事や日常生活での生き生きとした姿を集団の成長として話しましょう。(個人を褒めたい場合は会の終了後に親さんに声を掛けて話せると良いです。)
課題点は「ここが駄目」という言い方にならないように「この点は3月までに更に成長させたい」と、願いを語る形で伝えるとよいです。
クラスへの願いを話すとき「学年で1番になる」とか「元気で活発に」という方向性は望ましくないと思います。これだとおとなしい子の親は「うちの子はこの先生に付いていけないのでは?」と不安になります。
「誰もが伸び伸びと過ごせる温かいクラス」という方向性なら、活発な子もおとなしい子も大切にされると感じられます。日頃からそういう学級経営を心掛けましょう。
担任の話の最後に家庭へのお願いを話します。
生活リズムを整えることや学習習慣を付けることが中心になると思います。中学校だとスマホの使い方、小学校だと宿題を見てもらうといったお願いも必要かもしれません。
親への啓蒙も学校の役割の一つなので、きちんとお願いしましょう。ただ家庭によっては難しい場合もあるかもしれないので、押し付けと思われないように優しい言い方を意識しましょう。
保護者の質問に答える
担任の話が終わったら「私の話は以上です。何か疑問や質問がありましたら伺います。」と言います。ここで質問があれば答えます。
質問に答える際に気を付けることは「学校全体や他の教員に関わることはその場で答えず持ち帰ること」です。もちろん学校全体で共通理解できていること、決まっていることは答えますが。
質問を持ち帰る場合は「回答を学級通信でお伝えします」と言います。保護者個人が分かればよいことなら「回答をお電話させていただきます」と伝え、忘れずに電話をします。
学級経営やクラスの様子についての質問はその場で答えます。
保護者同士の意見交流
次に保護者同士の交流の場を設けます。交流と言ってもテーマを決めて話し合えと言うのでは親さんたちがとまどってしまいます。
「お子さんの最近の様子や、学校、クラスについて感じていらっしゃることを一言ずつ話していただけませんか?〇〇さんから席順でお願いします」と、何でもいいから話すように促します。
保護者の話はにこやかにうなづきなら聞きましょう。
先に質問の時間を取りましたが、その時には質問が出ないことも多いです。でも個人で話し出すと課題を含んだ話をする人が実は多いです。
「『勉強しなさい』と言わないと勉強を始めません」「スマホをいつも触っていて気になります」「部活ですごく疲れてダラダラしています」「最近反抗的です」等。そうした話は素早くメモします。
全員が話し終わったあとで「〇〇さんの話の中で……ということがありましたが、他のお宅ではどうですか?」と全体に振ります。「うちの子も同じです」「うちではこのようにしています」という話をワイワイしてもらいます。
話し合いが終わったら担任が締めます。保護者から出た話をまとめ「私の方からも子供たちに……を気を付けるように話しますね」と言います。(まとめるのは難しくないです。授業のまとめを話すのと同じです)
翌日生徒たちに「昨日学級懇談会でお母さんたちがこんなことを言っていたよ。心当たりのある人はいるかな」と言い、改善してほしいことを伝えます。
懇談会で親同士の交流の場を設けると案外時間がかかります。日程を確認しつつ取り入れてください。
まとめ
長くなったので要約します。
①学級懇談会はプレッシャーかもしれませんが「案ずるより産むがやすし」気楽にやって大丈夫です。
②学級懇談会は「保護者の思いを交流する」「担任の思いを理解してもらい安心してもらう」という場です。
③学級懇談会の進め方
・クラスの様子、担任の願いを話す。
・保護者からの質問を聞く。(質問が出なければ出ないでよし)
・保護者に一言ずつ話してもらう。
・保護者の話から課題を見つけてそれについて交流してもらう。
・担任がまとめを話す。
学級懇談会のことを考えると気が重い、という方は多少気楽になったでしょうか。ベテランの先生方にはあまり参考にならなかったかもしれませんが、このくらいラフにやっても懇談会が成立するという意味で参考にしてください。
ところで、学級懇談会に参加する保護者が少ないとやる意義がないのでは?と思ったことはないですか?
いいえ。参加が少なくても学級懇談会をする意義はあります。親同士のつながりは教員が想像する以上に強いからです。
部活をやっている子の親同士は連絡用のグループLINEを持っています。大多数の保護者が幼稚園や保育所の頃からママ友同士のつながりを広げています。
ですから学級懇談会に参加しない保護者も、参加した保護者から会の内容や雰囲気を聞くことができます。
参加していない保護者が参加した保護者に「どうだった?クラスは?担任は?」と聞いて「特に問題なさそうだよ」と返事をもらったら、それで安心してもらえます。
参加した保護者が10人いなくても、その人たちが「問題なさそう」と感じれば、クラスの大半の保護者に安心が伝わります。参加が少数でもその人たちに安心が伝わる会にしましょう。
難しい準備をしなくても安心は伝えられます。
今回の記事は以上です。
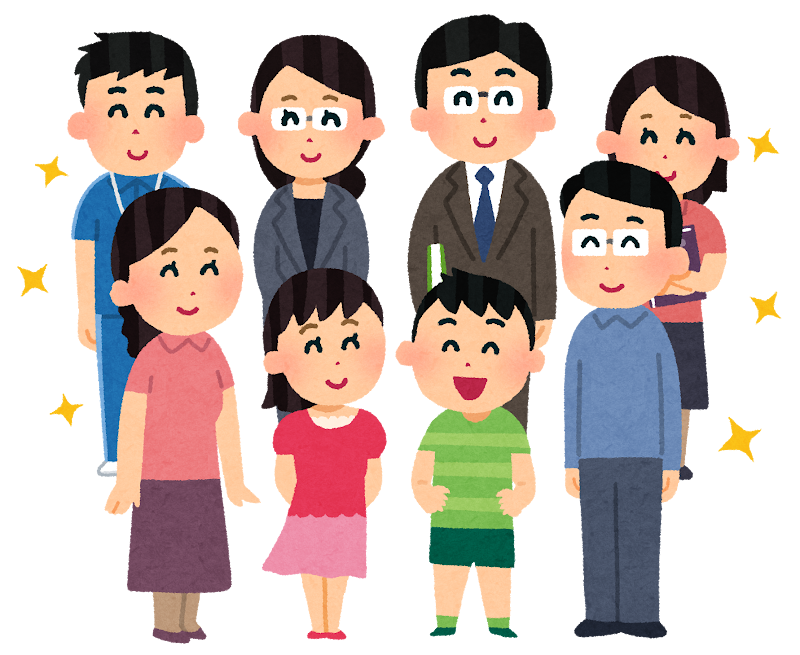

コメント