教員の仕事は何かとストレスが溜まります。
精神疾患で休職する人もいて、学校の人手不足に拍車がかかっている現状もあります。
こんな時代だからこそ先生方は自分の身を自分で守っていきましょう。

ストレスを減らすために心がけたいことを思いつくだけ書いてみました。
ぜひ参考になさってください。
気の持ちようが大事
何事も気の持ちよう、というのは本当にそうです。
人生万事塞翁が馬、禍を転じて福と為す、今は辛くてもぱっと開けることがあるのが人生です。
気を楽に持ちましょう。
言い訳をしよう
運が悪かった。ああなるよりはまだましだ。まだ若いんだから(もう年だから)仕方がない。等々、言い訳をするのはみっともないものです。
でも、自分を追い詰めて自分も周りも不幸にするよりは、逃げ口上を言って逃れた方がずっと良いです。
そうやって自分を甘やかし、許せるあなたは賢いです。いつかどこかで挽回すればいいし、挽回できます。
悔しいけれど今は諦める、という考えもときには必要です。やれる範囲のことはやっているんだから100%納得できなくてもそれでいいのです。
私自身、37年間の教員生活を振り返ると、あのときはどう頑張ってもあれ以上はできなかったな、と思うことがたくさんあります。時間も環境も限られていますからね。
積極的に手を抜こう
手を抜かない、納得いくまでやりきる、という姿勢は大切です。
でも学校の先生が本気でそれをやろうと思ったら、1日が100時間あったって足りません。
生徒全員を高いレベルに引き上げるのは生徒の能力差を考えたら最初から不可能です。Aさんはここまで、Bさんはここまで、とどこかで線を引くしかありません。
1日は24時間だし勤務時間もあるのだから、その範囲でできることしかできません。
自分なりにこだわる部分はあると思いますが、量的、時間的に無理なことはやらない、と割り切りましょう。
楽になるように学ぼう
仕事のストレスが一番強いのは「慣れない時期」です。初任で経験がない頃が一番大変で、年を追うごとに楽になります。
慣れていない頃が大変なので、新しい学校に転任した年もストレスが強いです。その学校に慣れるまで少し苦労します。
他にも、校務分掌が初めてとか、担任したクラスでいじめ問題が初めて起きたとか、慣れない状況はいくらでも出てきます。
そんなときに「嫌だ嫌だ」と思っていると辛いだけです。新しい経験をするときは「ここで自分なりのやり方を掴もう。そうすれば次に同じことがあっても対処できるようになる」と考えましょう。
経験することで慣れる(成長できる)という意識を持つとやる気が出ます。新しい経験をするたびに自分なりの方法を見つけて今後に生かしましょう。
そういう前向きさを持つと教師の仕事は面白くなります。次々と新しい経験ができ、年々慣れて成長できる仕事だからです。
成長するためには、面倒でも記録を残して次回に生かせるようにします。
授業なら、授業の流れのメモやそのとき使った資料やプリントを保管し、次回も使えるようにしましょう。
生徒の問題で学年で動いたなら、色々な先生がどういう指導をしたか、自分の分かる範囲でメモします。疑問に思ったことは質問して、指導の仕方の全体像を理解しましょう。
若いうちは重要な役割を担うことはありませんが、指導の意味を理解して動くことはとても大事です。いつか重要な校務分掌が回ってくるので、いつでもできるように学びましょう。
授業も生活指導も学ぶべきことはいくらでもあります。書籍でもネットでも役に立ちそうなものはチェックして、真似できるところはどんどん真似しましょう。自分流にアレンジできるところはして指導に生かしましょう。
職場の人に対してイライラしない
自分なりに一生懸命やっていると、職場の人に不満を感じることがあります。
なぜあの人はやらないのか、協力してくれないのか、こっちに仕事を押し付けるのか、生徒にあんな態度を取るのか、等々。
意見してやろうか、でも揉めるのは面倒だしと悶々とする、なんてことがあります。
これは本当にまずい、困る、ということ以外は放っておきましょう。不要な仕事やイライラを増やす必要はありません。
本当に困ったときは、一人で解決するのではなく誰か頼りになりそうな人に相談しましょう。
健康を守る行動をしよう
体力も精神力も充実していて仕事が楽しいという人はよっぽど大丈夫だと思いますが、気付かぬうちに無理をしていることもあるので、健康には十分気を付けましょう。
元気に頑張っている先生が50代で病休になるとか、最悪亡くなるということがあります。
私も50代のときに癌を患って休んだことがあります。幸い早期発見で手術をし、短期間で職場に戻り、今もこうして元気に定年後生活を楽しんでいます。
人生は長いです。自分の体と心を守りながら教員生活を送ってください。
健康診断を受ける
私が癌を患ったとき、早期発見で事なきを得たのは人間ドックのおかげです。要精密検査の判定をもらって「めんどくせー!」と思いましたが、ちゃんと病院に行って良かったです。
ストレスに耐えながら仕事を続けてきて、早死にしたら目も当てられません。周囲に遠慮などせずに、年休を取って病院に行きましょう。
ちなみにですが、人間ドックで要精密検査判定だったときは、まずかかりつけ医(風邪をひいたときなどに行く近所の医院)に相談しましょう。
「人間ドックで要精密検査の判定をもらってしまいましたが、どうしたらいいでしょう」と言えば検査をしてくれます。
かかりつけ医で検査ができない場合は詳しい検査のできる病院を教えてくれます。私のときはかかりつけ医がその病院に電話をし、紹介状を書いてくれました。
楽しみを持つ
私は結婚して子供もいるので、仕事との両立は本当に大変でした。
子供が小さい頃はそれを理由に部活は副顧問にしてもらい、頼れる主顧問にほとんど任せていました。自分の母と旦那の母が孫育てをしてくれたので、かなりの部分を任せていました。
それでも自分の時間はほぼない状態でした。けれど自分の時間が僅かでも、その僅かな時間を楽しむことはしていました。
若い頃はテレビゲームが好きで、結婚しても子供ができても少しずつやりました。子供が大きくなってから、とある男性アイドルグループにはまり推し活を楽しんできました。
僅かな時間でも仕事とは別の楽しみがある、というのは精神衛生上非常に良いと感じます。教員は仕事にとても多くの時間を取られますが、家族との時間や趣味の時間が少しでもあることで、心をリセットできる気がします。
時間がないからと言って仕事に人生のすべてを捧げてはいけません。「仕事は私の趣味です!」という境地に達している人はその限りではないかもしれませんが、私はその境地には行けませんでした。
食事を大切に
教員は時間がないです。時間がないと食べるものに気を遣っていられませんよね。
でも私は癌を患ってから考えを改めました。癌は恐ろしい病気です。再発したら嫌だと思いました。生活習慣病は食事が原因の部分も多いと聞きます。だから色々な本やネットで調べました。
ストレスを避けること、食べ物に気を付けることが大切だということが多く書かれていました。教員がストレスを避けることは難しいので、せめて食べ物に気を付けようと思いました。
それがどれだけの効果があったかわかりませんが、罹患後7年経って再発はしていません。ささやかな変化ですが、次のことに気を付けるようになりました。
・朝食は「菓子パンとコーヒー」だったのを「バナナ、ヨーグルト、グラノーラとトマトジュース」に替えた。
・給食はしっかり食べるので、夕食を抑えて(特に炭水化物を減らして)バランスを取った。
・アルコールは一切飲まない。インスタントラーメンや甘い飲料はほとんど口にしない。
現役の頃はこんな程度です。退職した今は自分で食事を作るので、栄養バランスや食べる量はより気を付けられるようになりましたが、シニアの食事紹介のブログではないのでこのくらいにします。
睡眠をとる
睡眠は大切だと思いますが、正直よくわかりません。
適切な睡眠は7時間と言われることもありますが、そんなに上手く眠れたことがないです。決まった時刻に寝て決まった時刻に起きたいですが、寝付けない夜もあるし早く目覚めてしまう朝もあります。
テレビを見ていたら「『自分は布団に入ったらすぐに眠れる』と言う人は慢性的に睡眠不足だから寝落ちしているのです」と専門家の方が言っていました。「布団に入って10分ほどで眠るのが良い睡眠です」とも。
いや、難しいって。寝付けない日が続いて睡眠不足、翌日はバタンキューで寝る、の繰り返しが多いです。
私の結論は「毎日一定の睡眠が取れるに越したことはないがあまり気にしても仕方がない」です。
ただ現役の先生の中には「ストレスが強く寝付けない日が多くて辛い」という人がいると思います。無理せず年休を取ってお医者さんに相談しましょう。(これが一番言いたいことです。)
オンオフを明確にする
教員は仕事を家に持ち帰ったり休日でもクラスのことを考えてしまったりしがちです。できるだけやめましょう。
ただ、楽しいことなら構わないと思います。授業や行事が上手くいって気分がいいなら何度でもそのときのことを思い出しましょう。
授業を良くするために、あんなことしようこんなことしようと考えるのが楽しいときはいくらでもすればいいです。
でも、やらないと仕事が終わらないから持ち帰ったとか、クラスの問題が気になって頭から離れない、というのはストレスになります。
私も若いときはそんなこともありましたが、いつからかやめました。仕事の道具は持ち帰らない、家で仕事のことは考えない、仕事は学校で終わらせます。
私が現役のときは仕事が終わるまで学校に残ってやっていました。帰る時刻は日によって違いましたが19時台に退勤することが多かったです。
明日の授業はどうしよう、と家で考えるのは精神衛生上良くないので、学校でしっかり準備をしてから帰りました。
最近は形だけの働き方改革で「早く帰りましょう」と管理職に言われることが多いですが、行事、会議、研修などの仕事を減らさずに、早く帰れと言われても困りますね。
私が勤めていた学校では、多くの先生が無視して残業していました。褒められることではないですが、家に仕事を持ち帰るよりはストレスは少なかったです。
職場に働きかけよう
ストレスを軽減するには職場の働き方改革が必要です。なかなか難しい職場もあるかもしれませんが、行動しなければ何も始まりません。
行動の仕方について書くので参考にしてください。
思っていることを口に出す
職場で発言することは職場の状況によっては勇気がいるかもしれません。それでも色々な場面で発言することは大事です。
案外賛同を得られるかもしれませんし、口に出すことで気持ちがすっきりするかもしれません。
ただ、誰かから反論されて落ち込む可能性もあるので、空気を読んで黙っていた方が良い場合もあります。そこは状況を見極めましょう。
発言しても大丈夫そうなら、自分のストレスが減るような提案をさり気なく口に出してみます。
「この仕事はやらなくてもいいですよね」「これは明日やればいいですね」みたいなことをさらっと言ってみましょう。職員室で日頃から「ああいうことは良くない」「こうすればいいのにね」と発言することも心がけましょう。
同僚の先生方に「この人はこういう考えの人だ」と理解してもらえると、いろいろな場で発言しやすくなります。
打ち合わせや会議で、仕事が増えそうな提案がなされたとき「すみません。それは確かに生徒のためになることですが、学力の低い子には負担が大きくないですか?」といったことを発言してみましょう。
先生の負担が増えるからやめてほしい、と言うのは気が引けますが、子どもや保護者のことを考えた発言なら説得しやすいです。同僚の先生が援護してくれる可能性も高いです。
言っても通らないこともありますが気にしてはいけません。間違ったことでなければ問題ないですし、教員の負担を減らすという考えには賛同してくれる人が必ずいます。そういう考えの人が増えれば職場は過ごしやすくなるでしょう。
自分の校務分掌でできる改革をする
働き方改革で仕事を減らし、ストレスを減らしたいものです。まずは自分の校務分掌でできることを考えましょう。
例えば自分が図書館担当だとします。図書委員会の活動で全員の先生に本の紹介を書いてもらい、放送したり掲示したりすることが恒例になっているとします。
これはどう考えても先生方の負担になる活動なので、今年度からは図書委員や本をよく読んでいる生徒が本の紹介を書くことにする、という具合です。
どの校務分掌にも改善できることはあるはずなので、改革していきましょう。
人に頼る
自分の手に余ることは遠慮せずに他の人に相談しましょう。自分の力でできそうなことも人に頼ってみる、くらいの気持ちでもいいかもしれません。
自分一人で何とかしなければならないという思い込みはストレスの元です。他の先生方と協力する(=頼る)のが当たり前だと考えましょう。
中学校の担任なら、まず学年主任や同学年の先輩教員に相談。相談の内容によっては校長、教頭、教務、生徒指導主事、校務分掌の担当者、養護教諭、相談員、校務員等々に相談。
あまり話したことがないから相談しづらいと感じる人もいるかもしれませんが、相談内容とマッチした相手ならきっと親身になって答えてくれます。
クラスに扱いづらい生徒がいて困っていることを、他学年の仲良い先生に話してもそれはただ愚痴を聞いてもらっているだけです。学年主任や同学年の先生に話せば「あの子はねえ……」と役に立つアドバイスがもらえる可能性が高いです。
場合によっては「私から注意するよ」「私の授業でも働きかけるよ」「あの子の親と部活で会えるから話してみるよ」等、思いもよらない強力な援護がもらえる可能性すらあります。
とにかく他の先生に話すことで助けてもらえますし、問題を共有することで気持ちが楽になります。一人で抱え込まないことが自分の身を守ることに繋がります。
自分一人で何とかしようとしては駄目ですよ。
最後に
いろいろ書いてきましたが、私が定年退職まで37年勤められたのは「運」と「楽天的な性格」と「家族」のおかげです。どれ一つ欠けても途中で退職していたと思います。
現役の先生方の中には辞めたいと思っている人もいるかもしれません。それも人生の選択なので良いと思いますが、できれば退職まで勤めてほしいです。
教員はお金を使う暇がないので、余程の浪費家でない限り貯金は貯まります。退職金や年金ももらえます。安定した老後を送れる可能性が高いので頑張ってほしいです。
でも体を壊したら元も子もないのでそれだけは気を付けて、ちょっと図々しいくらいの精神で乗り切ってください。
もしもどうしても耐え切れなくなったら、転職するという選択肢もあります。
こちらのサイトを眺めてみてはどうでしょう。
「就いてよかった仕事ランキング」https://jobuddy.jp/contents/detail/ranking_of_the_best_jobs_i’ve_had
実際に転職するかどうかはともかく、精神的に追い詰められたときは現実逃避すると気持ちが楽になります。
くれぐれもご自分の心と体を大切に。陰ながら応援しています!


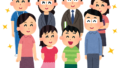
コメント